自社の業務に合わせた条件分岐項目を追加

フォームを作成する際、ご要望されることが多い「条件分岐」の項目。先に入力された内容に応じて、次に表示される質問や選択肢を切り替える仕組みです。
例えば、最初に「所属部署」を選んでもらって、「営業部」の方には営業に関連する設問を、それ以外の部署の方には別の設問を表示する、といった使い方ができます。
とても便利な仕組みですが、設計が複雑になりやすく標準機能だけでは対応しきれないケースも出てきます。
特に大きな企業では部署や役職によって業務フローが細かく分かれていることが多く、「誰に何を聞くべきか」の設計がそもそも難しい、ということもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、備品購入申請フォームを例に、「こういう分岐ができると便利そう」という仮のケースをご紹介しつつ、導入時のポイントについてまとめてみました。
想定ケース:備品購入申請フォームをもっと使いやすく
社内で使う備品の購入申請を、1つのフォームで受け付けているとします。
営業部・経理部・人事部など、すべての部署で同じフォームを使うような場合ですね。
一見シンプルですが、実際にはこんな困りごとがありそうです。
- 自分に関係ない設問が多くて、記入が面倒
- どこをどう書けばいいのか分からず、ミスや漏れが発生
- 管理部門での確認・差し戻しが多く、やり取りに時間がかかる
こうした状況を改善するために、フォームに条件分岐を取り入れてみるという選択肢があります。
提案:部署ごとに最適な入力フローをつくる
例えば、最初に「所属部署」と「備品カテゴリ」を選ぶ設問を用意し、その回答によって次の入力項目を切り替えるようにします。次のようなイメージです。
- 営業部の場合は、「端末の利用目的」や「訪問先での使用有無」などを表示
- 経理部の場合は、「会計処理方法」や「見積書の有無」などを表示
- 人事部の場合は、「設置場所」や「利用人数」などを表示
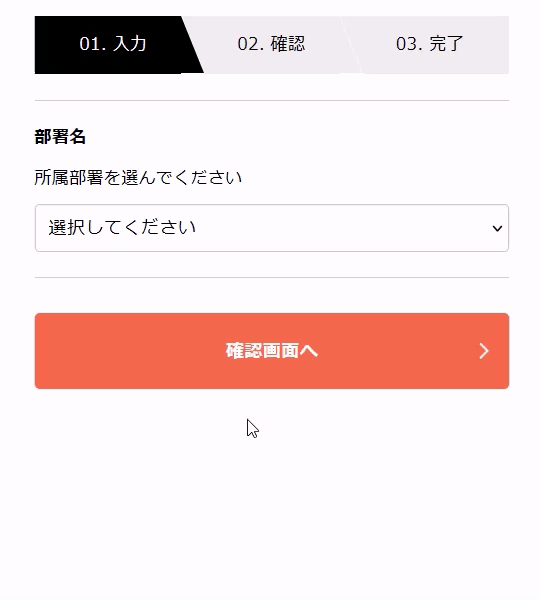
このように、それぞれの部署で本当に必要な情報だけを聞くように設計することで、次のような効果が期待できます。
- 記入の負担を減らせる
- 記入ミスが減る
- 管理部門側での確認がスムーズになる
導入時のポイント:カスタマイズはなぜ必要?
条件分岐を使えばフォームはかなり柔軟になりますが、いざ導入しようとすると、次のような工夫が必要になります。
- 分岐のロジックが複雑になりがち
複数の選択肢や条件が絡むと、「どのパターンで何を表示するか」をしっかり整理する必要があります。 - 標準機能ではカバーしきれないことも
フォームツールによっては「複数条件の組み合わせ」や「通知内容の切り替え」などに制限がある場合があります。 - 事前のヒアリングが重要
部署ごとにどんな困りごとがあるか、どんな情報が本当に必要かをきちんと聞き取っておくことで、無理のない設計ができます。
こういった理由から、実際の業務に合わせてしっかり設計するには、ちょっとしたカスタマイズが有効なのです。
まとめ:業務に合わせた条件分岐で、フォームがもっと使いやすく
標準のフォームだけでは対応しづらい業務の複雑さも、条件分岐を活用することで柔軟に対応できるようになります。
とくに、複数の部署が共通で使用する申請フォームの場合、「誰に・何を・どの順番で聞くか」をきちんと設計するだけで、申請の精度も確認の効率も大きく変わります。
「入力がわかりにくい」「申請に時間がかかっている」「差し戻しが多い」などのお悩みがある場合は、単にフォームを作るのではなく、業務に合わせた条件分岐の設計を検討してみてはいかがでしょうか。
